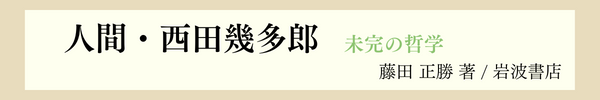「のっぺらぼう」の経済から「表情豊か」な経済へ【前編】

SDGs経営やESG経営を標榜する企業が増える今、難解と言われる「西田幾多郎」哲学が改めて注目を浴びています。真に生きるとはどういうことか?を追究した西田。今回は、西田哲学研究の第一人者である京都大学名誉教授の藤田正勝氏を迎え、効率性を追求する合理主義的な思考だけでは辿り着けない、これからの社会イノベーションに必要な視座と哲学について語り合いました。(対談日:2021年12月28日)
今、危機的状況にあるのは地球ではなく人々の意識
熊野:衣食住足りて物質的に豊かになった日本でも、未だに自殺や生活習慣病で亡くなる方が絶えません。真に危機的なのは、人々の意識や価値観と言えるのではないでしょうか。
「自分や周りの人間さえ豊かに幸せになればいい」という利己的な考えに傾倒し、人間の欲望が肥大化した結果、地球環境は破壊され、孤独が広がり、社会全体が不幸になってしまいました。資源枯渇や気候変動など、様々な制約条件が高まる今、本当の持続可能社会を迎えるためには、哲学的な思考に基づき人々の価値観をシフトする必要があると感じています。「個人が幸せになればなるほど社会は不幸せになる逆立性の社会」から「個人が幸せになればなるほど社会も幸せになる共立性の社会」への移行が急務です。その時の企業に必要な視座や役割は何か?ということを改めて考えたいと思います。
藤田氏:これまでは物質的豊かさが優先され、経済発展と社会課題解決の共立が困難な時代であったと思います。戦後、経済は格段に発展しましたが、一方で一人ひとりの人間が「真の豊かさ」を感じにくくなったように思われます。
現代社会では、おっしゃる通り、欲望が肥大化しやすくなりました。もちろん欲望を持つから様々なことが実現できたり、社会が発展した面もあるので、一概に欲望を否定するわけではありません。しかし、必要以上に消費欲求を促すメディアや広告などにより、私たちは昔に比べてはるかに欲望に踊らされるようになってしまいました。
「足るを知る者は富む」という老子の言葉があります。欲望を追求する人ではなく、持っているもので満足ができる人こそが豊かだという意味ですが、東洋の伝統的な思想の中で重視されてきた考え方です。しかし経済発展をきっかけに、私たちの社会では欲望や成長こそが是とされるようになりましたが、欲望には限りがありません。一つ望むものを獲得しても、さらに大きなものが欲しくなります。私たちはこの欲望の連鎖の中に巻き込まれて、そこから抜け出せなくなってしまいました。そのために私たちは、本当の意味での豊かさや生きがいを感じることができなくなってしまったように思います。
熊野:そうですね。近代的な工業技術は大発明で、欲望と同じく決して悪いものではありません。しかし、工業が発展し、モノや情報が増えた社会では「欲望の質」が変わったように思います。あるモノで満足する必要はなく、無数に選択肢がある中で常に欲望を満たす何かを探す。探せば探すだけ、何かが見つかるので「もっと望ましいものがあるのでは」とキリがない。それこそ老子の言葉とは正反対ですよね。
「人と自然をコストとしない」倫理観とは
熊野:事業家として「経済成長か社会課題解決か」という二項対立のメカニズムから脱却し「持続可能な経済成長」という共立の時代を再構築しなければならないと強く感じています。そこで「あらゆる対立概念は不可分である」と考える西田の哲学にヒントがあるように思います。
近年、SDGsやESGによってビジネスにおいても徐々に人や自然が重視されるようになってきました。しかしそれでも、依然として収支の上では、人や自然は「人件費」「原料費」として経費の欄に載る、すなわちコストとしての扱いをされています。このメカニズムを前提に人々が貨幣的・物質的リッチさを求めた結果、今の逆立性の社会につながったと感じています。人と自然、その豊かな関係性は、本来コストとして計上するものではなく、むしろ最上の価値として位置づけられるべきです。
藤田氏:哲学的な視点から見ても、高度に発達した現代の資本主義の一番大きな問題は、人間や自然を資源、すなわち単なる利用価値として見てしまうところにあると思います。発展や成長を追い続けた結果、人間一人ひとりの存在の意義や価値が希薄になり、不明確になってしまったと思います。
では、その人間の存在の意義や意味とはいったい何でしょうか?それは私たちが生きていく上で感じる「生きがい」というものに深く関わっていると思います。「生きがい」は自分自身が抱いている願望が実現されたときにも、自分の持つ可能性が実現されたときにも感じますが、それが他者の喜びや幸福と結びついているときに、私たちは本当の意味での「生きがい」を感じるのではないでしょうか。つまり「生きがい」や人間の存在意義というのは、一人ひとりの人間の中においてではなく、他者とのつながりの中で他者に働きかけ、他者から働きかけられる、そういう関係性の中で考えられるのではないでしょうか。
熊野:「誰かのために」という気持ちですよね。第2次世界大戦後の日本では、荒廃した国や経済を再興するときに「自分の欲望を優先し、世間に迷惑をかけてまで金儲けすることは恥ずかしい」という社会動機が経済動機より優先されていました。ところが私の感覚では、1970年の万博以降「経済的に豊かにならなければ世間に恥ずかしい」という経済動機が優先される時代になったように感じるのです。
しかし、アフターコロナにおいて、特に若い世代の人々の意識は、関係性を壊してまで経済性を優先するのではなく「豊かな関係性があってこそ豊かな経済が成立する」という価値観に変わっていくと思います。現在デジタルネイティブと呼ばれる世代にとっては、物心ついたころから地球環境が危機的と言われていたり、コロナ禍で親の仕事が失われたりと、外的要因による幸福感への影響が非常に大きい。こうした環境で育った若者は、社会によい仕事がしたいという想いや、家族や友達や仲間を大切にしたいという内的な豊かさやつながりを求める気持ちが強くなっている気がしています。
「社会の内在化」を通じて豊かな関係性を生み出すには?
熊野:経済成長のみを追求する時代は終わり、特に若い世代を中心に「豊かな関係性のための豊かな経済」を求める声が大きくなってきていると感じます。今まさに、我々企業は何のために存在するのだ?という「レゾンデートル」を問われていると言えるでしょう。こうした時代に、企業はどのように価値を創っていくべきなのか、そのヒントとなる西田哲学の視座をご教示いただけますでしょうか。
藤田氏:そうですね。"豊かな関係性こそが豊かな社会をつくる"という熊野さんの考え方には非常に共感します。西田は、欲望に踊らされた自己の在り方を「偽我」という言葉で表現しています。欲望を追求していくと、ときに、あるいは必然的に他者との関係を壊してしまう。そうではなく、欲望を押さえ偽我を脱し、他者との関係を生み出していく...そこに「真に生きる、善く生きる」道があるのだと彼は考えていました。
西田は、個人主義と共同主義は相反するものではなく、根本的には同一だと言っています。偽我という利己主義の状態では、個人の中に社会が取り込まれていない、つまり内在化されていません。しかし西田が言う本当の個人主義とは、社会との関係性の中で個人が個人らしさを追求することを指します。それは決して他者を否定することではありません。自分らしさの追求が他者の幸福にもつながっているのです。
西田は何か絵空事を語っているように受け取られるかもしれませんが、私は決してそうではないと思います。そのような観点から、ちょっと面白い話がありますので、それを紹介します。発達心理学を研究している米国エール大学のポール・ブルーム教授が、エール大学乳幼児研究所で行った研究です。生後5カ月くらいの赤ん坊に、他人の手助けをする人形と、それを阻もうとする人形が登場する劇を見せたところ、ほとんどの赤ん坊が前者の人形を好んだというのです。まだ自分一人では行動ができない生後数カ月の赤ん坊にも、本性的な共感能力・利他性が備わっているという結論をブルームさんはそこから導き出しています。ここからも、私たちが本来他者について配慮し、他者と共に生きることを目指す存在であることが言えるように思います。
もちろん本来備わっている利他性・倫理観がそのまま大人になっても受け継がれていくわけではありません。人間の中には、自己中心主義と言いますか、利己性も存在します。私たちにはこの利他性と利己性という二つの原理が働いていると言ってもよいでしょう。そのはざまの中で私たちは生きているのです。
熊野:個人の中にも様々な個性、ダイバーシティがあるということですよね。非常によくわかります。私は事業において、そのはざまの中でも人々が利他性を安定的に発揮できる方法を考えています。そこで注目したのが、英国の人類学者ロビン・ダンバーが提唱する「ダンバー数」という定説です。「人間の脳が人間関係を理解できる範囲はおよそ150人が限界である」とするこの説に基づき、東日本大震災の被災地である宮城県南三陸町で、ある社会実験を行いました。
ライフラインが不安定な被災地では、まずエネルギーが必要です。そこで、誰もが出す生ごみを発酵してメタンガスを生み出すことができれば、暖もとれるし電気も使えるなと。まず、比較的津波の被害が少なかった高台の100人程度の集落の方々に、生ごみを発酵しやすいように異物がない状態に分別して、回収場所までお持ちいただくことをお願いしました。分解できない卵の殻や骨や貝は取り除いてくださいと。震災後の大変な時期に面倒くさいことを依頼していたので、最初は我々も分別のお手伝いをしていました。ところが、10日ほど経ったころに住民の方から「もう大丈夫だよ、自分たちでできるよ」と言われまして、任せきりにしていたら、その後ずっと、ほぼ100%異物のない状態で生ごみが回収できたんです。住民の方同士で声を掛け合ったり工夫したりしてくださって、これには、役場の方も驚かれていました。
藤田氏:150人という枠の中では、他を意識することができる...すなわち、それぞれの人の顔や性格も思い浮かび、利他性がうまく機能するのですね。その枠を超えてしまうと、同じ人間ではあるけれども、匿名性が高く名前の無い、言うなればのっぺらぼうな存在になってしまう。うん、よくわかります。
熊野:スケールメリットを重視する工業社会において、このような丁寧な関係性よりも効率性や規模を選んだ結果、不幸な社会を招いてしまったと感じます。
藤田氏:自分の前にいる人が、あるいは自分の行為を受け取る人がどういう人なのかがわからなければ、当然利他性は働きにくくなります。製品を作り、それを使う人がどんな顔をして、どんな生活をしているかということよりも、買ってくれさえすればよいということになってしまいます。買う側も同じですね。どんな人がどんな気持ちで作ったものなのか分からなければ、とにかく安いものがいい、となる。関係の分断による匿名性が、私たちの社会に大きな変化をもたらしたと言えるのかもしれません。
効率性と言えば、AIが人間の能力を凌駕する時点、つまり技術的特異点(シンギュラリティ)がやがて来ると言われています。将来、これまで人間が担ってきた役割がAIにとって代わられる...そういう時代は間違いなくやってくると思います。しかし、AIの能力がいかに大きくなっても、人間が持つ尊厳や価値は失われないでしょう。AIがどれだけ効率性で人間を凌駕しても、AIが人間に置き換わるということはありません。人間ができてAIにはできないことがあるからです。たとえば「他者への思いやり」や「愛」といったものです。
他の動物とは違って、人間が最も人間らしい点とは、自分の状態にしても、自分の行為にしても、様々な可能性を同時に思い浮かべ、その中でどれが一番自分にふさわしいかを考えることができるという点にあります。動物は「いま・ここ」に縛られていますが、人間は複数の、いや無限に多くの「いま・ここ」を思い浮かべ、その中から最も良いものを選択することができるのです。それは人間が自らの視点からモノを見るだけではなくて、その視点を離れて他者の視点に立つことができるということを意味します。「自分がこうしたい」ということだけではなく、他者がどのように感じ、何を望んでいるのかを考え、他者の気持ちに寄り添い、配慮することができるのです。AIにはそれができないと私は考えています。
おそらく「思いやりとはこういうことだ」とか「愛とはこういうことだ」とコンピュータ上で定義すれば、AIは人間と同じ行為をすることができると思います。しかしそれは、私たちが他者の苦しみや悲しみを自分のこととして感じとり、他者のことを思いやって行う行為とは根本的に違うものだと言えるでしょう。他者のことを自分のこととして考える、そのプロセスが重要なのです。
熊野:量子コンピュータなど科学的な領域でも、一元的に白黒つけるのではなく、不可分な部分を容認するような、複雑性を含む科学技術が生まれています。技術によって社会が完全に情報管理化されないために重要になるのが、哲学という視点だと思います。
藤田氏:AIが超えられない人間の価値として、もう一つ「ひらめき」があげられます。ひらめきにおいても、先ほど申しあげた思考のプロセスがとても重要な意味を持っています。私たちは、人生で一見無駄に思えるようなことも含めて様々な経験をします。その中で、考えもしていなかったもの同士の結びつきがあるときふと生まれるのです。まったく違ったときに、違った文脈の中でなされた経験なのに、それがあるとき、ふと結びつくということが起こるのです。効率だけを重視するやり方からは、そのような思いがけない結びつきは得られないと思います。
熊野:確かに効率性という領域のみで勝負すると、人間はAIに負けてしまうと思います。しかし、論理だけでは説明ができないことや、不確実で非連続なモノやコトのつながりにクリエイティビティは潜んでいます。今まで考えもしなかったような新しい発想やイノベーションは、これまでの効率重視のやり方では実現が難しい気がします。後半は、これから来たる社会において、イノベーションを起こすにはどのような視座が求められるのかについてお話しできればと思います。
対談者
藤田 正勝 氏(京都大学名誉教授)
1949年生まれ。1978年京都大学大学院文学研究科単位取得満期退学。1982年ドイツ・ボーフム大学哲学部ドクター・コース修了(Dr. Phil.)。1983年名城大学教職課程部講師。1988年京都工芸繊維大学工芸学部助教授。1991年京都大学文学部助教授。1996年同大学院文学研究科教授。2013年同大学大学院総合生存学館教授。
『人間・西田幾多郎----未完の哲学』(岩波書店、2020年)、『はじめての哲学』(岩波ジュニア新書、2021年)、『親鸞 その人間・信仰の魅力』(法蔵館、2021年)など、著書多数。
参考図書
アミタグループの関連書籍「AMITA Books」
【代表 熊野の「道心の中に衣食あり】連載一覧
【代表 熊野の「道心の中に衣食あり」】に対するご意見・ご感想をお待ちしております。
下記フォームにて、皆様からのメッセージをお寄せください。
https://business.form-mailer.jp/fms/dddf219557820